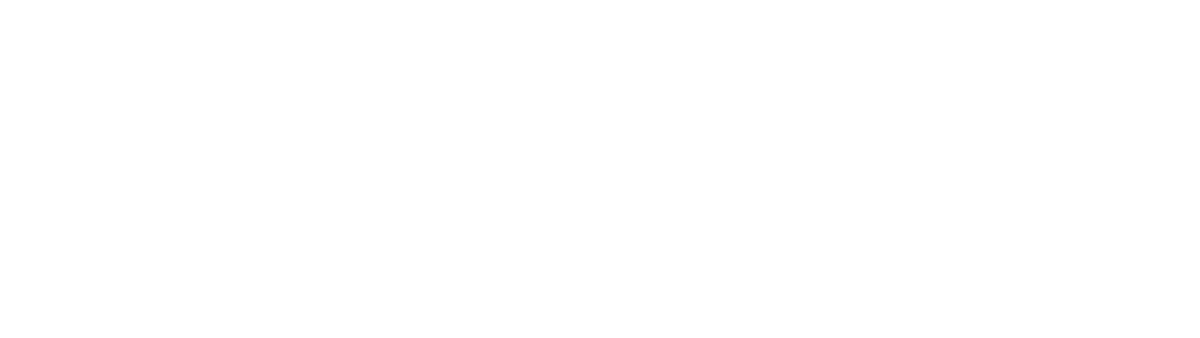- ブログ
歯周病セルフチェック10項目!気づかぬうちに進行する危険性
歯周病とは?静かに進行する口腔内の危険な疾患
歯周病は、細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患です。歯の周りの歯ぐき(歯肉)や、歯を支える骨などが溶けてしまう病気で、気づかないうちに進行していきます。
実は、30歳以上の成人の約80%がかかっていると言われる国民病なのです。むし歯と違って、進行してもほとんど痛みが出ないため、自覚症状がないまま進行していることが多いのが特徴です。
歯周病の一番の原因は、歯と歯の間にたまる歯垢(プラーク)です。歯垢の中にすんでいる細菌が毒素を出し、歯と歯肉の間に入り込んで歯ぐきに炎症を起こします。その炎症が進んでいくと、歯の周囲の歯根膜を溶かし、歯を支えている歯槽骨組織を破壊し、最終的には歯が抜けてしまうのです。
歯周病は単なる口の中の病気ではありません。近年の研究では、歯周病が全身の健康にも大きな影響を与えることがわかってきました。心臓疾患や脳血管疾患、糖尿病など、さまざまな全身疾患との関連性が指摘されています。
歯周病セルフチェック10項目!自分でできる簡単診断
歯周病は自覚症状がないまま進行することが多いため、定期的なセルフチェックが重要です。以下の10項目をチェックして、あなたの歯周病リスクを確認してみましょう。
思い当たる症状が多いほど、歯周病が進行している可能性が高くなります。早期発見・早期治療が大切ですので、心当たりのある方は歯科医院での検診をおすすめします。
1. 歯を磨くと血が出ることがある
歯磨きの際に出血があるのは、歯肉に炎症が起きている証拠です。健康な歯肉なら、多少強く磨いても出血することはありません。歯周病の初期症状として最も多いのがこの歯肉からの出血です。
「少し血が出るくらい大したことない」と思っていませんか?実はこれは歯周病菌と白血球の戦いの証なのです。放置すると、歯垢は歯周ポケットの中に潜り込み、どんどんと歯周組織を破壊していきます。
2. 歯と歯の間に食べ物が詰まりやすい
歯と歯の間に食べ物が詰まりやすくなったと感じたら要注意です。歯周病が進行すると、歯と歯の間の歯肉が下がり、隙間ができやすくなります。
以前は気にならなかった場所に食べ物が挟まるようになったら、歯周病の進行を疑いましょう。特に肉類が挟まりやすくなったと感じる場合は、歯周ポケットが深くなっている可能性があります。
3.歯肉が腫れることがある
健康な歯肉は薄いピンク色で、引き締まっています。歯周病になると歯肉が赤く腫れ、ブヨブヨとした感触になります。
腫れは炎症の典型的な症状です。歯肉の腫れが頻繁に起こる、または長期間続く場合は、歯周病が進行している可能性が高いでしょう。特に体調が悪かったり疲れたりすると歯肉が腫れるという方は、免疫力の低下と歯周病の関係を疑う必要があります。
4. 動く歯がある
歯がグラグラと動くようになったら、歯周病がかなり進行している証拠です。歯を支える骨が溶けてしまい、歯の安定性が失われている状態です。
歯の動揺は歯周病の中期から後期の症状で、放置すると最終的に歯が抜け落ちてしまう可能性があります。一度失われた歯の周りの骨は元に戻りにくいため、早急な治療が必要です。
5. 口臭が気になる、または人から指摘されたことがある
歯周病が進行すると、歯周ポケット内の細菌が増殖し、強い口臭の原因となります。自分では気づきにくいこともありますが、周囲の人から指摘されることもあるでしょう。
口臭の原因はさまざまですが、歯磨きや舌磨きをしっかり行っても改善しない口臭は、歯周病を疑う必要があります。特に朝起きた時の口の中のネバネバ感と口臭が強い場合は、歯周病の可能性が高いでしょう。
歯周病セルフチェックの続き:さらに5つの重要サイン
6. 冷たいものが歯にしみる
歯周病が進行すると、歯肉が下がり、歯の根元が露出することがあります。根元には象牙質があり、エナメル質で覆われている歯の表面より刺激に敏感です。
虫歯がないのに冷たいものがしみる場合は、歯肉の退縮による知覚過敏の可能性があります。これは歯周病の進行によって起こる典型的な症状の一つです。
7. 硬いものを噛むと歯が痛む
歯周病が進行して歯を支える骨が減少すると、噛む力が歯に適切に分散されなくなります。そのため、硬いものを噛んだときに痛みを感じることがあります。
これは歯の周りの組織が炎症を起こし、敏感になっているサインです。また、歯の動揺が始まっている場合も、噛むときに痛みを感じやすくなります。
8. 歯肉の色が赤い、または黒っぽい
健康な歯肉は薄いピンク色をしていますが、歯周病になると炎症によって赤くなります。さらに進行すると、酸素供給が不足して黒っぽく変色することもあります。
特に喫煙者の場合、歯肉が黒ずむことがありますが、これは血流が悪くなっているサインかもしれません。タバコは歯周病のリスクを高める大きな要因の一つです。
9. 歯肉が下がり、歯が長くなった気がする
「以前より歯が長くなった気がする」という感覚は、実は歯肉が下がっている証拠です。歯周病が進行すると、歯肉が退縮し、通常は見えない歯の根元部分が露出してきます。
歯肉の退縮は一度起こると元に戻りにくいため、これ以上進行させないためにも早めの治療が必要です。見た目だけでなく、知覚過敏や根面カリエス(根元の虫歯)のリスクも高まります。
10. 歯肉がぶよぶよしている
健康な歯肉は引き締まっていて弾力がありますが、歯周病になると炎症によってぶよぶよとした感触になります。指で軽く押すと、へこんだままなかなか戻らないこともあります。
また、歯肉を押すと血や膿が出ることもあります。これは歯周ポケット内に炎症が起きている明らかなサインです。
歯周病の危険因子:あなたはリスクが高い?
歯周病になりやすい人、進行が早い人には、いくつかの共通する因子があります。以下の項目に当てはまる方は、特に注意が必要です。
これらの危険因子を持っている場合は、より頻繁な歯科検診と徹底した口腔ケアが重要になります。自分のリスクを知ることで、予防意識を高めましょう。
糖尿病との深い関係
糖尿病と歯周病は密接な関係にあります。糖尿病の方は歯周病になりやすく、また歯周病が糖尿病を悪化させるという双方向の関係があります。
血糖値が高い状態が続くと、体の抵抗力が低下し、歯周病菌に対する防御機能も弱まります。さらに、歯周病になると炎症性物質が血液中に放出され、インスリンの働きを妨げて血糖コントロールを難しくします。
実際、2025年3月に発表された研究では、歯周病治療を受けている糖尿病患者は、治療を受けていない患者と比較して、人工透析に移行するリスクが32〜44%低いことが明らかになりました。歯周病治療が糖尿病の合併症予防にも役立つ可能性が示唆されています。
喫煙の影響
喫煙は歯周病の最大のリスク因子の一つです。タバコに含まれるニコチンやタールは歯肉の血流を悪くし、免疫機能を低下させます。そのため、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病になるリスクが約2.5〜6倍も高くなります。
また、喫煙者は歯肉からの出血などの初期症状が現れにくいため、気づいたときには重症化していることも少なくありません。さらに、治療効果も出にくく、再発率も高いという特徴があります。
歯ぎしり・くいしばり
歯ぎしりやくいしばりは、歯に過剰な力をかけ、歯周組織にダメージを与えます。特に歯周病がある場合、すでに弱っている歯を支える組織に余計な負担をかけることになります。
夜間の歯ぎしりは自分では気づきにくいものですが、朝起きたときの顎の疲労感や頭痛、歯の摩耗などが見られる場合は疑ってみるべきでしょう。歯科医院でマウスピースを作製することで、歯ぎしりによる歯周組織へのダメージを軽減できます。
歯周病が全身に及ぼす影響:口の中だけの問題ではない
歯周病は単なる口の中の病気ではありません。全身のさまざまな疾患と関連していることが、近年の研究でわかってきました。歯周病が引き起こす可能性のある全身疾患について見ていきましょう。
歯周病菌や炎症性物質が血流に乗って全身をめぐることで、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。口腔ケアは全身の健康維持にも重要なのです。
心臓疾患・脳血管疾患との関連
歯周病は心筋梗塞や脳梗塞などの血管疾患のリスクを高めることがわかっています。歯周病の人はそうでない人の2.8倍も脳梗塞になりやすいというデータもあります。
歯周病原因菌などの刺激により動脈硬化を誘導する物質が出て、血管内にプラーク(粥状の脂肪性沈着物)ができ、血液の通り道が細くなります。プラークが剥がれて血の塊ができると、その場で血管が詰まったり、血管の細いところで詰まったりして、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす可能性があるのです。
糖尿病の悪化
先ほども触れましたが、歯周病と糖尿病は密接に関連しています。歯周病菌は内毒素をまき散らし、これが血管内に入ると血糖値に悪影響を及ぼします。
内毒素は、脂肪組織や肝臓からのTNF-αという物質の産生を強力に推し進めます。TNF-αは、血液中の糖分の取り込みを抑える働きもあるため、血糖値を下げるホルモン(インスリン)の働きを邪魔してしまうのです。
一方で、歯周病治療を行うことで血糖コントロールが改善することも報告されています。糖尿病患者さんにとって、歯周病治療は糖尿病治療の一環と考えるべきでしょう。
認知症との関連
最近の研究では、歯周病と認知症との関連も指摘されています。2025年3月に国立長寿医療研究センターから発表された研究によると、歯周病によって認知機能が低下し、認知機能低下により歯周病も悪化するという「歯脳相関」があることがわかりました。
歯周病菌のひとつであるP.g菌(Porphyromonas gingivalis)がもつ「ジンジパイン」というタンパク質分解酵素は、アルツハイマー病悪化の引き金をもつ可能性が示唆されています。
高齢になるほど口腔ケアが難しくなり、認知機能が低下すると適切な歯磨きができなくなるという悪循環も問題です。認知症予防のためにも、口腔ケアは重要なのです。
歯周病予防のための日常ケア:今日からできること
歯周病は予防が最も重要です。日常的なケアを見直し、歯周病のリスクを減らしましょう。以下に、効果的な予防法をご紹介します。
これらの予防法は特別なものではなく、日常生活に取り入れやすいものばかりです。継続することで、歯周病のリスクを大幅に減らすことができます。
正しいブラッシング法
歯周病予防の基本は、毎日の正しいブラッシングです。歯と歯肉の境目(歯肉溝)に歯ブラシの毛先を45度の角度で当て、小刻みに動かすようにみがきましょう。
力を入れすぎると歯肉を傷つけたり、歯の表面を削ってしまったりするので注意が必要です。一度に磨く範囲は2〜3本分にとどめ、時間をかけて丁寧に磨くことが大切です。
電動歯ブラシの使用も効果的です。特に高齢者や認知機能が低下している方には、手磨きより効率的に歯垢を除去できる電動歯ブラシがおすすめです。
歯間ブラシやフロスの活用
歯ブラシだけでは、歯と歯の間の歯垢を完全に除去することはできません。歯間ブラシやデンタルフロスを併用することで、歯ブラシの届かない部分の清掃が可能になります。
歯間ブラシは、歯と歯の間のスペースが比較的広い場合に適しています。一方、歯と歯が密着している部分にはデンタルフロスが効果的です。自分の口腔状態に合わせて、適切な清掃用具を選びましょう。
定期的な歯科検診
歯周病は自覚症状がないまま進行することが多いため、定期的な歯科検診が非常に重要です。健康な方でも、少なくとも3ヶ月に1度は歯科医院でチェックを受けることをおすすめします。
プロによるクリーニング(PMTC)を定期的に受けることで、自分では取りきれない歯垢や歯石を除去できます。また、歯科医師や歯科衛生士から、あなたの口腔状態に合わせた適切なケア方法のアドバイスも受けられます。
特に糖尿病や心疾患などの全身疾患をお持ちの方は、より頻繁な検診が必要かもしれません。かかりつけの歯科医師と相談して、適切な検診間隔を決めましょう。
まとめ:早期発見・早期治療が歯周病対策の鍵
歯周病は静かに進行する病気ですが、適切なケアと定期的な検診によって予防や早期発見が可能です。今回ご紹介した10項目のセルフチェックを定期的に行い、少しでも気になる症状があれば、早めに歯科医院を受診しましょう。
歯周病は単なる口の中の問題ではなく、全身の健康にも影響を及ぼす重要な疾患です。特に糖尿病や心疾患などの全身疾患をお持ちの方は、歯周病のリスクが高まるため、より注意が必要です。
正しいブラッシング、歯間ブラシやフロスの活用、定期的な歯科検診など、日常的なケアを継続することが、歯周病予防の基本です。また、喫煙や過度の飲酒、不規則な生活習慣なども歯周病のリスクを高めるため、生活習慣の改善も重要です。
歯は一度失うと二度と再生しません。失った歯を入れ歯やブリッジなどの治療で補うと、他の歯に負担がかかり、やがて総入れ歯になっていくリスクもあります。大切な歯を守るためにも、歯周病対策は欠かせません。
当院では、歯周病の予防から治療まで、患者様一人ひとりの状態に合わせた最適なケアをご提供しています。歯周病でお悩みの方、予防に関心のある方は、ぜひオーラルデンタルクリニック川崎までご相談ください。
あなたの大切な歯を守り、健康な生活をサポートするために、私たちは常に最新の知識と技術で対応いたします。